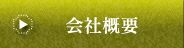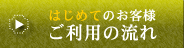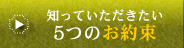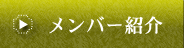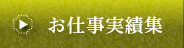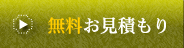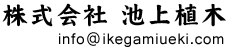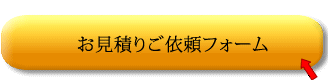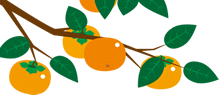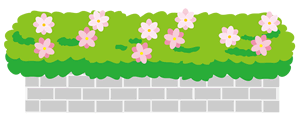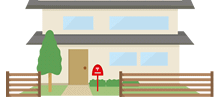施肥(栄養補給)
森林土壌は肥料をあげなくても、生態系※で自然に育ちます。鉢植え内は、養分を蓄える土壌が貧弱なため、栄養が不足しがちです。植物を大きく、美しくするには、適度な養分が必要です。ただ植物は光合成で自ら栄養を生み出せるので、あくまで栄養補給と考えます。
※枯れ葉、虫の死骸、動物の排泄物等が土に栄養を補給し、植物が育つサイクル。
植物の足りない栄養分を補給するために用いられるものを指します。肥料には植物の三大要素の窒素(N)・リン酸(P)・カリ(K)が含まれているものが多く、化学的に合成されて速効性がある「化学肥料(化成肥料)」と、植物性または動物性由来の原料で作られていて、土の中で微生物に分解されるため、効き目は緩やかですが持続性が高い「有機質肥料」の2つに分けられます。
─肥料を与えるタイミング
肥料を与えることを施肥と言い、元肥(もとひ)と追肥(ついひ)に分けられます。
元肥
元肥は植物を土に入れる前に肥料を施すこと。植え替え時に土に肥料を混ぜ、養分を補える土壌に近づけます。
追肥
追肥は育成状態で肥料を施すこと。生育度合いに合わせ、栄養を補います。
| 3月 | 4~10月 | 12~3月 |
| 生育準備期 | 生育期 | 休眠期 |
| 発芽を促す | 土がしっかり乾いてから。2週間に1回程度 |
─肥料の成分
肥料の主成分は、窒素・リン酸・カリウムの3つ。植物が最も必要とする養分です。部位が必要な成分を把握しておくと、肥料や活力剤の選別がしやすくなります。
A、一次要素
窒素(N)
窒素はタンパク質を作り、植物そのものを形作ります。葉・茎の生長に欠かせないです。
リン酸(P)
リン酸はDNA・細胞膜になる要素です。開花・結実を促進します。
カリウム(K)
カリウムは植物そのものに変化を与えませんが、体内の化学反応を促進。特に根を丈夫にします。

B、二次要素
カルシウム(Ca)・マグネシウム(Mg)・硫黄(S)
生育不良は二次要素不足が原因な場合もあります。
─肥料の種類
有機肥料は独特の匂いから、室内植物の肥料は化成肥料が主流です。
A、有機肥料
油かすや米ぬかといった植物性の有機物を原料としている肥料。魚粉や鶏糞といった動物性の有機物を原料としている肥料もあります。独特の臭いやコバエが湧きやすいので、植え替え時など元肥としてご使用ください。
B、化成肥料
原料は窒素・リン鉱石・カリウム鉱石といった無機物。液体と固体が主流で即効性があります。
1、固形肥料
固形タイプは土の表面近くに置いて栄養を補給します。液体肥料と違って、水やりする度に少しずつ溶けていくので即効性には期待できないものの、長くゆっくりと効果が持続します。
固形タイプは土の表面に置いて栄養を補給。水やりする度に少しずつ溶けるので、穏やかに効き続けます。
2、液体肥料
液体タイプは液体肥料や液肥と呼ばれ、土の中に流して栄養を補給します。アンプルを土に差すものや、ボトルから土に流し込むもの、葉に直接スプレーするもの、また水で希釈して散布するものなどがあります。春〜秋の生育期や、急な栄養不足時に使用されます。
液体タイプは土の中に流して栄養を補給。水で薄めて散布します。生育が早めますが、土に残りにくく持続性はないです。
3、活力剤
肥料では補えない、カルシウム・マグネシウム・硫黄、二次要素(ミネラル)を補給します。たとえば葉のツヤを良くするには葉緑素を作るマグネシウムが必要です。
─肥料を与える時期
生育期(4~10月)
生育期に当たる4〜9月は、継続的な栄養補給が必要です。2ヶ月に1度のペースで追肥します。
おすすめの肥料は、じわじわと効果を発揮する固形タイプです。購入する際は、「緩効性肥料」に分類される肥料を選ぶと失敗が防げます。
緩効性肥料とは、土壌内の肥料濃度を一定に保ちながら、効果を長期間にわたって持続させられる肥料を指します。商品によって持続する期間に差がありますが、迷った際は2ヶ月間持続するものを選ぶと良いでしょう。
休息期(11~3月)
肌寒さを感じるようになる11月頃は、2週間に1度のペースで追肥します。春・夏・秋と長期間にわたってぐんぐん生長してきた観葉植物は、この時期になると栄養とエネルギーが不足してお疲れモードに入ります。そのため、栄養価が高くて速効性のある液体肥料や化成肥料を追肥すると良いでしょう。